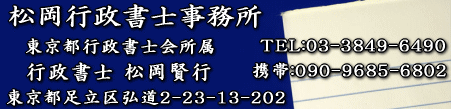初回電話ご相談料/30分5000円~(無料ご相談不可。なお、ご依頼は電話・メールで受付中。ご依頼以外の問合せはメールのみ受け付けています。) ※お電話受付(9:00~20:00、365日・土日祝日でも受付中)、eメールは24時間・年中受付中
eメールアドレス:officce.xm02〔アットマーク〕gmail.com
携帯電話(表示は下にあります)のショートメールからも受付ています。
(1)裁判紛争を起こさない契約書を作成するポイントは?
契約書の条文を設定するうえでの注意点とは
クーリング・オフ条項記載の契約書は、契約条項が特定商取引法で厳格に規制されています。
要するに、このように条項事項を記載しなければならない。
あるいは、このような条項は記載してはならない。
という具合に法律で規制されています。
ところが、この契約条項を設定するときに規制する法律条文の法律用語は抽象的に記載されています。
具体的に書かれていません。
たとえば、「名称」という法律用語があります。
法律を深く勉強している人なら、ピントきます。
これは一例なのですが、この法令解釈の間違いが原因でクーリンフ・オフがおきるのです。

法律の素養がない人は、日常使われている用語で広く解釈してしまうのです。
これは、頭が悪い良いの問題ではなく、法律用語をきちんと理解し使用しているかどうかの問題なのです。
まだ、「名称」なんかは、きちんと法律で使い分けができているので、問題ないのですが。
もっと抽象的な法律用語となると、学説や判例を調べなくてはなりません。
ところが、いろんなバリエーションの契約がありますので、すべてを判例が網羅されていることなんか稀なわけです。
判例がない場合はどうするかとうことですね。
なぜ、クーリンフ・オフがおこるのかということなのですが、これらのことを理解していないからなんです。
要するに、条文の設定を法律やそれを解釈する、学説、判例に則っていないからクーリンフ・オフがおこるんですね。
直感で契約書を作っているんですね。
(2)条文設定する上での注意点とは
六法全書などで、契約を規制する法律とその条文を調べる
この契約書の条文はこのような規制にしたがって条文を作るのであると、理解してから契約書を作らなければならないのです。
私は以前、法律とは畑違いの人から、その契約書の条項はおかしいのではないかと指摘を受けてときがあります。
では、法律の何条に基づいてその条項がおかしいのか根拠を示すように反論しましたが、返事はありませんでした。
根拠のない指摘だったんです。
イメージや直感ですね。
困ったものです。
この指摘した人は印刷屋さんなのですが、ついでに弁護士法違反ですよ。

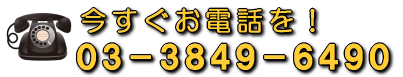 |
|---|